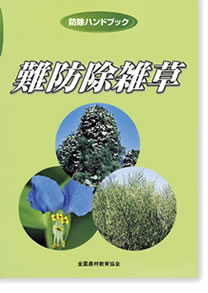
防除ハンドブックシリーズは、診断と防除を目的とした実用的な内容で、
技術者や農家など、防除の現場での使いやすさを追究したコンパクトなシリーズです。
最新の防除薬剤も紹介しています。
本書では、おもに農耕地等で、雑草を「手取り」や「道具を使用した防除手段」での防除が困難な草種ではなく、除草剤使用を前提として、防除に有効な剤が限られている種や除草剤の抵抗性が出現している種であり、かつ比較的広範囲で問題化している種を、「難防除雑草」として取り上げることとしました。
これら難防除雑草の生態を写真で解説するとともに、もっとも有効な防除法を解説しました。皆様の参考となれば幸いです。
| 雑草 |
イネ科カヤツリグサ科キク科ツユクサ科ヒルガオ科ナス科ウリ科ブドウ科マメ科アカネ科アカバナ科タデ科シダ植物(トクサ科) |
|---|
「雑草」は、私たちに身近な植物であり、誰もが知っています。そして、農業生産や私たちが生活するにあたって、存在すると不都合であったり、支障があったりするために、つねに排除の対象としてきた植物が雑草であります。実際、私たちは、人力、道具、機械や除草剤などあらゆる手段を用いて除草してきましたが、今日も雑草は存在し続けています。すなわち、雑草は人類に排除されにくい形質をもって今日まで生きつづけてきた植物とも言えます。言い換えますと、雑草は除草手段の弱点をついた形の草種や、その環境変化に適応した種へと変遷していきます。また、私たちの移動や物流が世界的規模で盛んになることにより、さまざまな国から雑草が侵入して定着するため、帰化雑草が増加しつづけています。私たちが合理的な雑草防除を行うには、雑草群落がその場に存続し続ける標徴的な草種と動的に変化して増加する草種から構成していることを念頭においておく必要があります。
また、雑草の害の程度や防除の重要性を表現する言葉として、「主要雑草」、「重要雑草」、「強害草」、「難防除雑草」、「Worst Weeds」、「Noxious weed」などがあり、それぞれの著者が定義をして使用される言葉であります。わが国においても、それぞれの場面や特性に応じて、「難防除雑草」が将来定義づけられることを望みたいと思います。
本書では、おもに農耕地等で、雑草を「手取り」や「道具を使用した防除手段」での防除が困難な草種ではなく、除草剤使用を前提として、防除に有効な剤が限られている種や除草剤の抵抗性が出現している種であり、かつ比較的広範囲で問題化している種を、「難防除雑草」として取り上げることとしました。
これら難防除雑草の生態を写真で解説するとともに、もっとも有効な防除法を解説しました。皆様の参考となれば幸いです。
(編者:佐合隆一、小山豊)
初版 2014年1月30日 公開
第二版 2021年7月20日 公開
最終更新日 2021年7月20日
| 小山豊 | (公財)日本植物調節剤研究協会 |
|---|---|
| 佐合隆一 | 茨城大学名誉教授 |
| 大隈光善 | (公財)日本植物調節剤研究協会 |
|---|---|
| 大島匡郎 | (公財)日本植物調節剤研究協会 |
| 金久保秀輝 | (公財)日本植物調節剤研究協会 |
| 吉良賢二 | 元(公財)日本植物調節剤研究協会 |
| 筒井芳郎 | (公財)日本植物調節剤研究協会 |
| 野口勝可 | 元 (独)農業・生物系特定産業技術研究機構中央農業総合研究センター |
| 穂坂尚美 | (公財)日本植物調節剤研究協会 |
| 村岡哲郎 | (公財)日本植物調節剤研究協会 |
| 山木義賢 | (公財)日本植物調節剤研究協会 |
| 山口晃 | (公財)日本植物調節剤研究協会 |
公益財団法人 日本植物調節剤研究協会、全国農村教育協会
全国農村教育協会
東京都台東区台東1-26-6 〒110-0016
電話03-3833-1821 Fax03-3833-1665
https://www.zennokyo.co.jp